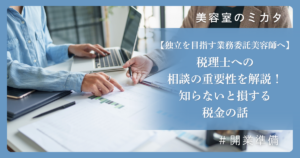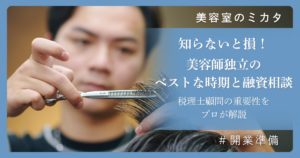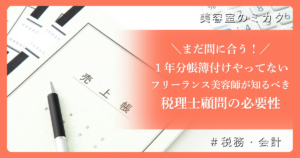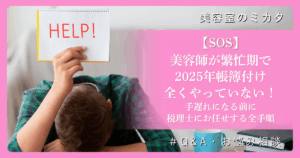【完全ガイド】美容師が雇用から業務委託になったときに読んで欲しい|手続き・税金・保険の全て

美容師として雇用から業務委託へ。働き方が大きく変わることに、期待と不安を感じていませんか?この記事では、開業届や保険・年金の切り替えといった複雑な手続きから、一番不安な税金(確定申告・経費・インボイス制度)の話まで、必要な情報を完全網羅しました。業務委託への移行は、事前に正しい知識を身につければ何も怖くありません。本記事が、あなたが安心して新しいキャリアをスタートするための完全ガイドです。
1. 美容師が雇用から業務委託へ 働き方はどう変わるのか
正社員やアルバイトといった「雇用」から「業務委託」へ。この変化は、単に契約形態が変わるだけでなく、美容師としての働き方、収入、そしてライフスタイルそのものを大きく変えるターニングポイントです。自由な働き方に憧れを抱く一方で、収入の不安定さや手続きの煩雑さに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。この章では、まず雇用と業務委託の根本的な違いを理解し、その上でメリット・デメリットを具体的に解説します。あなたが後悔のない選択をするための、最初のステップです。

1.1 雇用契約と業務委託契約の根本的な違い
これまであなたが結んでいた「雇用契約」と、これから結ぶ「業務委託契約」は、法律上の立場が全く異なります。この違いを理解することが、新しい働き方への第一歩です。
雇用契約は、あなたがサロン(会社)に「労働者」として所属し、サロンの指揮命令のもとで働く契約です。労働時間や休日、業務内容などが決められており、労働基準法によって守られています。毎月決まった給与が保証される安定性がある反面、働き方の自由度は低いと言えるでしょう。
一方、業務委託契約は、あなたが「個人事業主(フリーランス)」として、サロンと対等な立場で業務を請け負う契約です。サロンからの指揮命令はなく、あくまで「お客様への施術」という業務の完成に対して報酬が支払われます。そのため、働き方の自由度は格段に高まりますが、労働基準法の保護対象外となり、すべてが自己責任の世界になります。
1.2 業務委託美容師になるメリット
業務委託という働き方には、多くの美容師を惹きつける魅力的なメリットがあります。特に、これまでの働き方に窮屈さを感じていた方にとっては、大きなチャンスとなるでしょう。
最大のメリットは、収入が大幅にアップする可能性があることです。雇用契約に比べて歩合率(還元率)が50%〜60%と高く設定されていることが多く、あなたの技術力や指名客数がダイレクトに収入へ反映されます。頑張りが正当に評価される環境と言えるでしょう。
また、時間や場所の自由度が高いことも大きな魅力です。サロンの定休日や営業時間に縛られず、自分のライフスタイルに合わせて出勤日や休日を決められるケースがほとんどです。長期休暇を取って旅行に行ったり、プライベートな時間を充実させたりと、ワークライフバランスを実現しやすくなります。
さらに、朝礼やミーティング、後輩の指導といったサロン業務から解放され、お客様への施術に集中できる環境もメリットの一つです。人間関係のストレスが減り、純粋に美容師としてのスキルを追求したい方には最適な働き方かもしれません。
1.3 業務委託美容師になるデメリットと注意点
自由で高収入が期待できる一方で、業務委託には必ず理解しておくべきデメリットと注意点が存在します。メリットだけに目を向けて安易に移行すると、後で「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。
最も大きなデメリットは、収入が不安定になるリスクです。雇用契約のような固定給や最低保証がないため、指名や集客ができなければ収入はゼロになる可能性もあります。あなたの集客力と技術力がこれまで以上にシビアに問われることになります。
次に、社会保険や福利厚生がなくなる点です。会社員時代に加入していた健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険はすべてなくなり、国民健康保険と国民年金に自分で加入し、全額自己負担で保険料を支払う必要があります。怪我や病気で働けなくなった際の傷病手当金や、失業した際の失業手当もありません。
そして、確定申告などの事務作業をすべて自分で行う必要があることも忘れてはいけません。売上や経費の管理、年に一度の確定申告など、これまで会社がやってくれていた手続きをすべて自己責任で行う必要があります。お客様との万が一のトラブル対応も、基本的には自分自身で解決しなければならないという覚悟が必要です。
2. 雇用から業務委託へ 美容師がやるべき手続き完全ロードマップ
正社員やアルバイトといった雇用契約から業務委託へ移行する際には、これまで会社が代行してくれていた様々な手続きを自分自身で行う必要があります。具体的に「いつ」「どこで」「何を」すれば良いのか、やるべきことをステップ順に沿って解説します。このロードマップ通りに進めれば、スムーズに個人事業主としてのスタートを切ることができます。
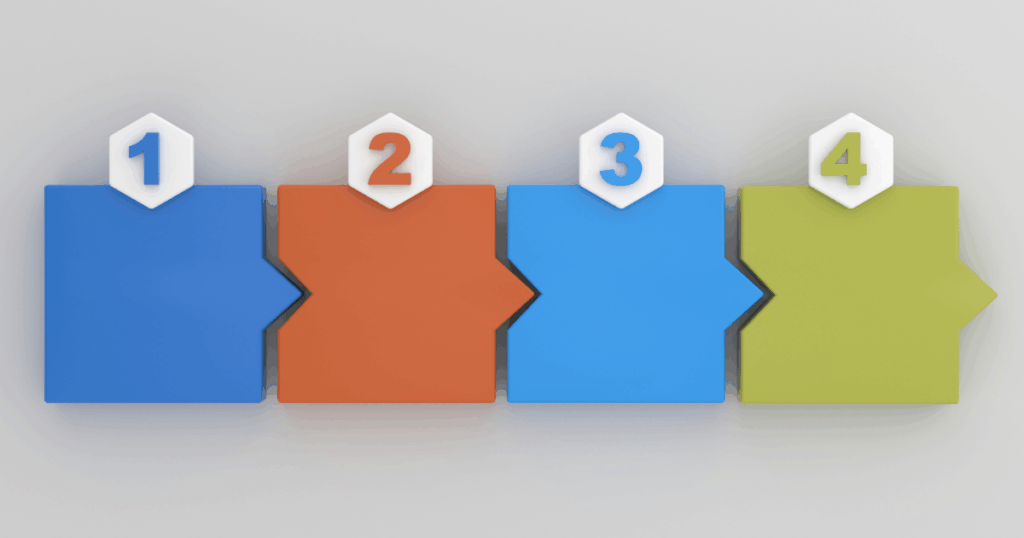
2.1 STEP1 退職時に確認すべきこと
業務委託美容師になる最初のステップは、現在勤めているサロンからの退職手続きです。同じ店舗で働き続ける場合でも、一度雇用契約を終了させる必要があります。退職時には、確定申告や各種手続きで必要になる以下の書類を必ず受け取りましょう。
- 源泉徴収票:確定申告で必ず必要になります。
- 雇用保険被保険者証:雇用保険の加入履歴を証明する書類です。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書:国民年金への切り替え手続きで使用します。
- 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険への加入手続きで必要です。
これらの書類は後の手続きで必須となるため、退職前に会社へ発行を依頼し、確実に受け取ってください。もし受け取れなかった場合は、速やかに元の勤務先へ問い合わせましょう。
2.2 STEP2 開業手続きをしよう
業務委託契約で働くということは、個人事業主になることを意味します。そのため、事業を開始したことを税務署に知らせる「開業手続き」が必要です。少し難しく感じるかもしれませんが、手続き自体はシンプルなので安心してください。
2.2.1 開業届の提出方法と書き方
個人事業主としてスタートするために、まずは「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称「開業届」を税務署に提出します。これは、あなたが事業を始めたことを公式に届け出るための書類です。
- 提出先:納税地(一般的には自宅の住所)を管轄する税務署
- 提出期限:事業を開始した日から1ヶ月以内
- 入手方法:国税庁のホームページからダウンロード、または最寄りの税務署で入手可能
書き方はそれほど難しくありません。屋号(お店の名前、なければ空欄でも可)や事業内容(「美容業」など)を記入します。提出方法は、税務署の窓口へ直接持参するほか、郵送やe-Tax(電子申告)でも可能です。
2.2.2 なぜ青色申告がお得なのか
開業届を提出する際に、必ずセットで「所得税の青色申告承認申請書」も提出しましょう。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、青色申告には税制上の大きなメリットがあります。
- 最大65万円の特別控除:課税対象となる所得から最大65万円を差し引くことができ、所得税や住民税を大幅に節税できます。
- 赤字の繰り越し:事業が赤字になった場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。
- 家族への給与を経費にできる:生計を同一にする家族に支払った給与を経費として計上できます(青色事業専従者給与)。
この申請書は、原則として事業開始から2ヶ月以内に提出する必要があります。開業届と一緒に提出すれば忘れる心配がありません。節税はフリーランス美容師にとって非常に重要なので、必ず青色申告を選択しましょう。
2.3 STEP3 保険と年金の手続き
会社員時代は給与から天引きされていた社会保険料ですが、個人事業主になると自分で保険と年金の手続きを行い、保険料を納める必要があります。退職後、速やかに切り替え手続きを行いましょう。
2.3.1 国民健康保険への切り替え
退職すると、会社の健康保険は使えなくなります。代わりに、お住まいの市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。手続きは以下の通りです。
- 手続き場所:住民票のある市区町村役場の担当窓口
- 手続き期限:会社の健康保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から14日以内
- 必要なもの:健康保険資格喪失証明書、本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバーカードなど
期限内に手続きをしないと、保険証がない期間が発生し、その間の医療費が全額自己負担になる可能性があるため、退職後すぐに手続きを済ませましょう。
2.3.2 国民年金への切り替え
会社員が加入する「厚生年金」から、個人事業主などが加入する「国民年金(第1号被保険者)」への切り替え手続きも必要です。こちらも国民健康保険と合わせて行いましょう。
- 手続き場所:住民票のある市区町村役場の担当窓口
- 手続き期限:退職日の翌日から14日以内
- 必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日がわかる書類(離職票など)、本人確認書類
国民健康保険の手続きと同じ窓口で同時に行える場合がほとんどです。保険料の支払いを忘れると将来受け取る年金額が減ってしまうため、忘れずに手続きを完了させましょう。
3. 美容師の業務委託で一番不安な税金の話 確定申告を徹底解説
雇用されているときは会社が全て行ってくれた税金の手続き。業務委託になると、これらを全て自分で行う必要があります。特に「確定申告」は、多くのフリーランス美容師が最初に戸惑うポイントです。しかし、仕組みさえ理解すれば決して難しいものではありません。ここでは、確定申告の基本から節税に繋がる経費の知識、そして最近話題のインボイス制度まで、税金の不安を解消するために必要な情報を分かりやすく解説します。
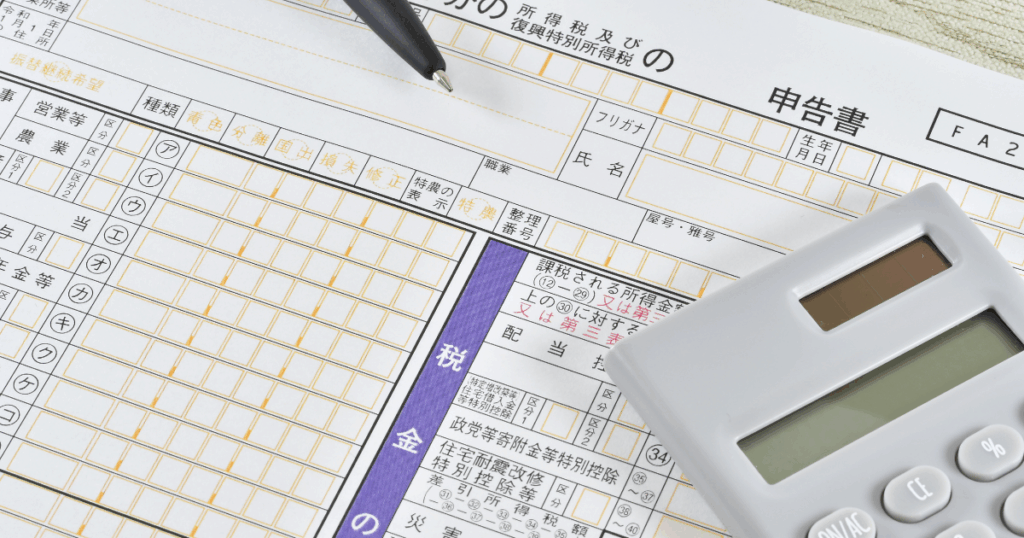
3.1 確定申告とは?いつ何をするのか
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の全ての所得(売上から経費を差し引いた儲け)を計算し、それに対する所得税額を算出して国に報告・納税する一連の手続きのことです。会社員は年末調整で会社が代行してくれますが、業務委託美容師は個人事業主となるため、ご自身で申告する必要があります。
申告と納税は、原則として所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。例えば、2023年1月1日〜12月31日までの所得は、2024年2月16日〜3月15日に申告・納税します。この期間に間に合うよう、日頃から売上や経費の記録をしっかりつけておくことが大切です。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出することで、大きな節税効果のある青色申告を選択できます。
3.2 美容師が経費にできるもの一覧
業務委託美容師にとって、経費を正しく計上することは最も重要な節税対策です。経費とは「事業(美容師の仕事)を行うために直接必要だった費用」のことです。何が経費になるのかをしっかり把握し、漏れなく計上しましょう。領収書やレシートは必ず保管してください。
- 消耗品費:ハサミやシザーケース、コーム、ダッカール、カラー剤やパーマ液などの薬剤、タオルなど。
- 新聞図書費:技術向上のためのセミナー参加費、美容業界の専門誌、マーケティング関連の書籍代など。
- 広告宣伝費:集客用のSNS広告費、ウェブサイトの維持費、名刺やチラシの作成費用など。
- 旅費交通費:セミナー会場への移動費、出張施術のための交通費、仕事で利用した駐車場代など。
- 通信費:仕事で使用するスマートフォンの利用料金、インターネット回線費用など。プライベートと共用している場合は、仕事で使う割合を計算して経費計上します(家事按分)。
- 接待交際費:モデルハントの際のお茶代、取引先との打ち合わせでの飲食代など。
- 地代家賃:自宅を仕事場の一部として使っている場合、仕事で使うスペースの割合に応じて家賃や光熱費の一部を経費にできます(家事按分)。
「これは経費になるかな?」と迷ったときは、「この支出が売上に繋がったか」という視点で判断するのが一つの基準になります。
3.3 所得税と住民税の仕組みと計算方法
確定申告によって納める税金は、主に「所得税」と「住民税」です。これらの税金がどのように計算されるのか、基本的な仕組みを理解しておきましょう。
まず、年間の「収入(売上)」から「経費」を差し引いて「所得」を計算します。ここからさらに、基礎控除や社会保険料控除などの「所得控除」を差し引いたものが「課税所得」となります。
所得税は、この課税所得に所得額に応じた税率を掛けて計算されます。日本の所得税は、所得が多いほど税率が高くなる「累進課税」が採用されています。
【所得税の計算式(簡易版)】
(収入 − 経費 − 所得控除)× 所得税率 − 税額控除 = 所得税額
一方、住民税は、確定申告の情報が市区町村に送られることで自動的に計算されます。そのため、ご自身で住民税の申告を別途行う必要はありません。住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず定額で課税される「均等割」の合計で決まります。納税通知書は、確定申告をした年の6月頃に自宅へ届きます。
3.4 2023年から始まったインボイス制度とは?美容師は登録すべきか
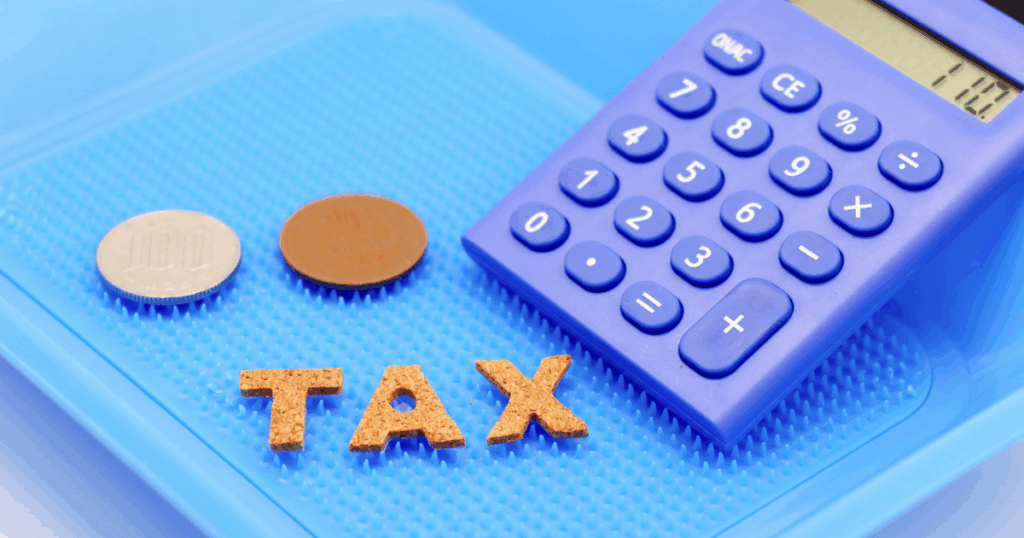
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の納税額を正確に計算するための新しい仕組みです。業務委託美容師も、この制度と無関係ではありません。
簡単に言うと、あなたが「インボイス登録事業者」になることで、取引先である美容室は消費税の納税額を抑えることができます(仕入税額控除)。そのため、取引先の美容室からインボイスの登録を求められる可能性があります。
インボイス登録事業者になると、これまで年間の売上が1,000万円以下で免除されていた消費税の納税義務が発生します。つまり、手取りが減る可能性があるということです。
登録すべきかどうかの判断は、以下の点を考慮しましょう。
- 契約している美容室がインボイス登録を求めているか
- 年間の売上が1,000万円を超える見込みがあるか
- 消費税を納税することによる収入への影響
最終的な判断は、ご自身の事業計画と、何よりもまず契約先の美容室の方針を確認することが重要です。契約内容に関わる大切なことなので、うやむやにせず、担当者としっかり話し合いましょう。
4. 社会保険はどうなる?美容師が知るべき保険と年金の全て
雇用から業務委託へ変わるとき、多くの方が不安に感じるのが「社会保険」や「年金」の問題です。会社員時代は給与から天引きされ、会社が半分負担してくれていたものが、全て自己管理・自己負担に変わります。ここでは、具体的に何がどう変わるのか、そして将来のために何をすべきかを分かりやすく解説します。正しく理解し、しっかり備えましょう。
4.1 雇用保険と労災保険はなくなる?
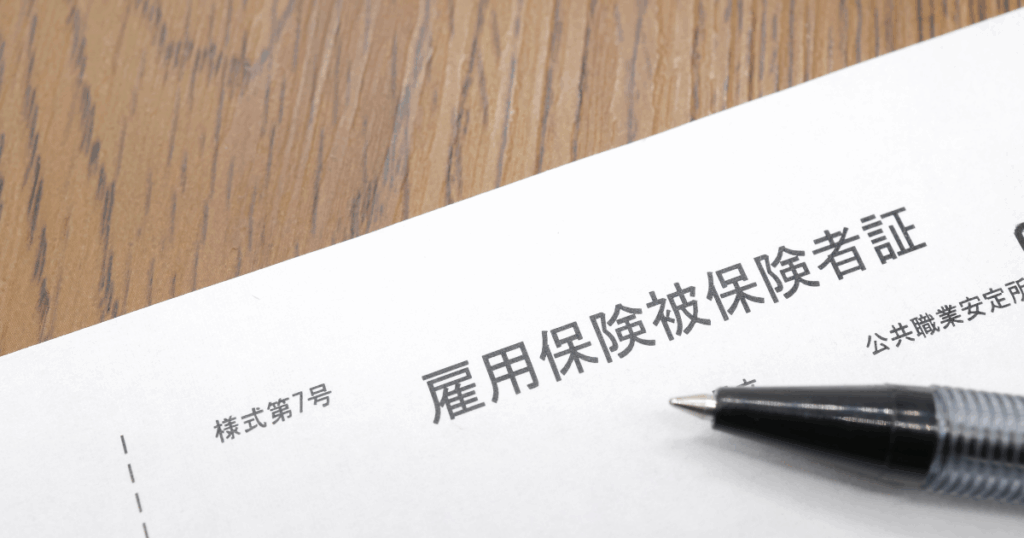
結論から言うと、業務委託契約になると雇用保険と労災保険(労働保険)には加入できなくなります。
なぜなら、これらの保険は「労働者」を保護するための制度だからです。個人事業主である業務委託美容師は、労働基準法上の労働者には該当しないため、対象外となります。
これにより、具体的には以下のような影響が出ます。
- 雇用保険:万が一、契約が終了して仕事がなくなった場合に受け取れる「失業手当(基本手当)」がなくなります。
- 労災保険:仕事中や通勤中にケガをしたり病気になったりした場合の治療費や休業補償が受けられなくなります。
ハサミで手を切ってしまったり、薬剤で手荒れが悪化したりといった美容師特有のリスクも全て自己責任となります。このリスクに備えるため、民間の保険への加入を検討する必要があります。
4.2 国民健康保険料はいくらになる?計算シミュレーション
会社を退職すると、それまで加入していた健康保険(協会けんぽや組合健保など)から脱退し、原則として市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。(退職後2年間は元の健康保険を任意継続する選択肢もあります)
気になる保険料ですが、国民健康保険料は前年の所得をもとに計算され、お住まいの市区町村によって保険料率が異なります。会社員時代は会社と折半でしたが、これからは全額自己負担となるため、負担額が増えるケースがほとんどです。
ここでは、簡単なシミュレーションをしてみましょう。
【モデルケース】
- 年齢:30歳
- お住まい:東京都新宿区
- 前年の所得(売上 – 経費):350万円
- 加入者:本人のみ
この場合、年間の国民健康保険料の目安は約38万円(月額 約3.2万円)となります。(※介護保険料を含まない概算。令和6年度の料率で計算)
所得が高くなれば保険料も上がり、上限額も設定されています。正確な金額を知るためには、必ずお住まいの自治体の窓口やウェブサイトで確認しましょう。国民健康保険料は、確定申告の際に全額「社会保険料控除」の対象となり、所得税や住民税を計算する上で節税に繋がります。
4.3 将来のために知っておきたい国民年金と付加年金
年金制度も、会社員が加入する「厚生年金(第2号被保険者)」から、自営業者などが加入する「国民年金(第1号被保険者)」に切り替わります。役所で国民健康保険への切り替えと同時に手続きを行いましょう。
注意すべき点は、国民年金は日本の年金制度の1階部分である「基礎年金」のみとなることです。厚生年金という2階部分がなくなるため、将来もらえる年金額は、会社員時代よりも少なくなります。
このままでは老後の生活が不安…という方は、以下の制度を活用して年金額を上乗せすることを強くおすすめします。
- 付加年金:毎月の国民年金保険料にプラス400円を上乗せして納めることで、将来「200円×納付月数」分が年金額に加算される制度です。2年以上受け取れば元が取れる、非常にお得な制度です。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):自分で掛金を決めて運用し、将来の年金資産を形成する制度です。最大のメリットは、掛金が全額所得控除の対象になるため、現役時代の所得税・住民税を大きく節税できる点です。
- 国民年金基金:国民年金に上乗せできる公的な年金制度です。iDeCoと同様に掛金は全額社会保険料控除の対象となります。
4.4 フリーランス美容師におすすめの任意保険
労災保険がなくなり、会社の福利厚生も受けられなくなる業務委託美容師は、自分自身で万が一のリスクに備える必要があります。特に以下の保険は、加入を検討する価値が高いでしょう。
- 所得補償保険・就業不能保険:病気やケガで長期間働けなくなった際の収入減をカバーしてくれます。体が資本の美容師にとって、最も重要な備えの一つです。
- 賠償責任保険:お客様にケガをさせてしまった、カラー剤でお客様の衣服を汚してしまった、お店の備品を壊してしまったなど、業務中の万が一のトラブルによる損害賠償に備える保険です。サロンが加入している場合もありますが、個人で加入しておくとより安心です。
- 生命保険・医療保険:会社員時代に加入したままになっている方は、保障内容が今の働き方やライフプランに合っているか見直す良い機会です。フリーランスは傷病手当金もないため、入院時の保障を手厚くするなど検討しましょう。
保険は安心を買うためのものですが、保険料は固定費になります。複数の保険会社の商品を比較し、自分の働き方や貯蓄状況に合った、無理のないプランを選びましょう。
5. 業務委託美容師として成功するために知っておきたいこと
雇用から業務委託への移行は、単に働き方が変わるだけではありません。あなた自身が「事業主」になるということです。ここでは、業務委託美容師として成功し、安定した収入と自由な働き方を手に入れるために不可欠な知識とノウハウを解説します。

5.1 契約書で必ずチェックすべき重要ポイント
業務委託契約書は、サロンとあなたの関係を定める最も重要な書類です。後々のトラブルを避けるため、署名・捺印する前に以下のポイントを必ず確認しましょう。口約束は避け、すべて書面に残すことが鉄則です。
- 報酬(業務委託料)の計算方法
指名売上とフリー売上の歩合率(還元率)が何%か、最低保証はあるのか、消費税は内税か外税かなど、報酬の計算方法を詳細に確認します。報酬体系や経費負担の範囲は、手取り収入に直結する最重要項目です。 - 経費の負担範囲
薬剤費、水道光熱費、タオル代、予約サイトの掲載料、クレジットカード決済手数料など、どこまでが自己負担になるのかを明確にしましょう。負担範囲によって実質的な手取り額は大きく変わります。 - 契約期間と更新・解除条件
契約期間はいつまでか、自動更新なのか、中途解約する場合のペナルティはあるのかなどを確認します。特に「一方的な契約解除」に関する条項は注意深く読み込む必要があります。 - 禁止事項(競業避止義務など)
契約中や契約終了後、近隣エリアでの独立開業や他店での勤務を制限される「競業避止義務」や、顧客情報の持ち出しを禁じる条項がないか確認します。あなたの将来のキャリアを縛る不当な制約がないかをチェックしてください。 - 損害賠償責任の範囲
お客様への施術ミスによるトラブルや、サロンの備品を破損してしまった場合の責任の所在と賠償範囲がどのように定められているかを確認しておきましょう。
もし契約書の内容に少しでも不安があれば、一人で判断せず、法テラスや弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
5.2 収入アップに繋がる集客方法とリピート戦略
業務委託美容師の収入は、あなた自身の集客力とお客様からの支持に大きく左右されます。サロンの集客に頼るだけでなく、自分を指名してくれるファンを増やすための主体的なアクションが不可欠です。
- SNSを活用したセルフブランディング
InstagramやTikTokなどを活用し、あなたの得意なヘアスタイルや技術、人柄が伝わるコンテンツを発信しましょう。ハッシュタグを効果的に使い、ターゲットとなるお客様にあなたを見つけてもらう仕組みを作ることが重要です。あなた自身のブランド価値を高め、指名客を増やすことが安定収入への鍵となります。 - 予約サイトのプロフィールを充実させる
ホットペッパービューティーや楽天ビューティなどの予約サイトは、依然として強力な集客ツールです。あなたのこだわりが伝わる自己紹介文や、質の高いスタイル写真を数多く掲載し、口コミへの丁寧な返信を心がけましょう。 - リピートに繋がるカウンセリングと次回提案
お客様の満足度を高め、再来店に繋げるためには、丁寧なカウンセリングが欠かせません。お客様の髪の悩みに寄り添い、ライフスタイルに合わせた提案をすることで信頼関係が生まれます。施術後には、次回のメンテナンス時期やおすすめのメニューを具体的に提案し、その場で次回予約を促しましょう。 - 既存顧客との関係維持
一度来店してくださったお客様との関係を維持することも大切です。LINE公式アカウントなどを活用して、来店後のアフターフォローやキャンペーン情報をお知らせすることで、お客様の記憶に残り、再来店へと繋がります。
5.3 困ったときの相談先一覧
個人事業主になると、契約トラブルや税金、経営に関する悩みなど、すべて自分で解決しなければなりません。しかし、一人で抱え込む必要はありません。専門家の力を借りることで、スムーズに問題を解決できます。
- 契約トラブル・法律に関する相談
契約内容が不当だと感じたり、サロンと報酬の支払いで揉めたりした場合は、法律の専門家に相談しましょう。
・法テラス(日本司法支援センター)
・地域の弁護士会 - 税金・確定申告に関する相談
確定申告のやり方がわからない、経費の範囲が知りたいなど、税金に関する疑問は税務の専門家が頼りになります。
・所轄の税務署(無料相談が可能)
・地域の税理士会
・青色申告会 - 経営全般に関する相談
集客方法や資金繰りなど、事業運営全般の悩みについては、公的な支援機関を活用できます。
・商工会議所、商工会
・よろず支援拠点
一人で抱え込まず、早い段階でそれぞれの専門家に相談することが問題解決への近道です。相談先を事前に知っておくだけでも、大きな安心材料になります。
6. 美容師が雇用から業務委託になるときのよくある質問
雇用から業務委託へ切り替わるタイミングは、期待とともに多くの疑問が生まれるものです。特に、お金や制度に関する不安は大きいでしょう。ここでは、多くの美容師さんが疑問に思う点をQ&A形式でわかりやすく解説します。
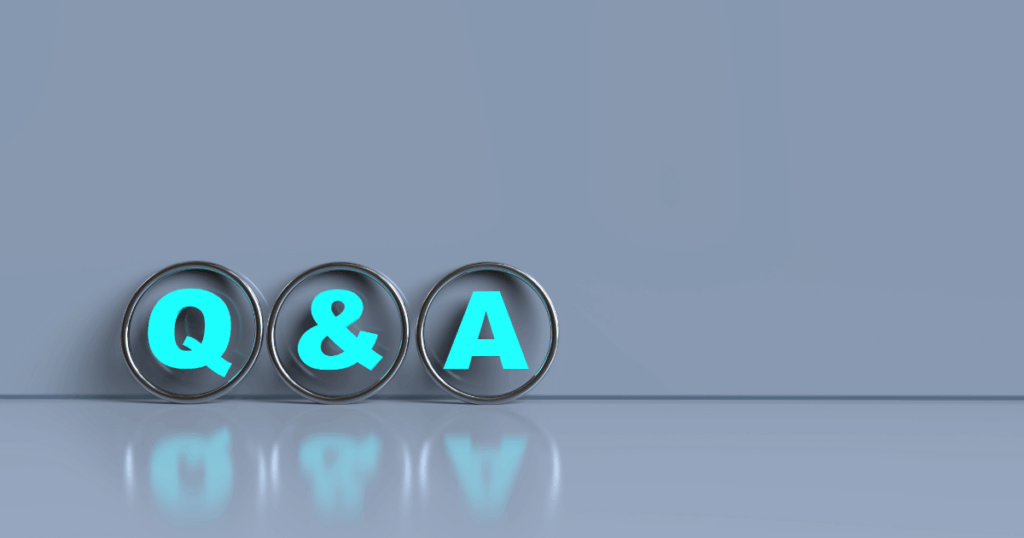
6.1 扶養には入れる?
配偶者の扶養に入れるかどうかは、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類で条件が異なります。
税法上の扶養は、あなたの年間の合計所得金額が48万円以下の場合に対象となります。業務委託の場合、売上から経費を差し引いた金額が「所得」です。例えば、年間の売上が150万円で経費が110万円かかった場合、所得は40万円となり、税法上の扶養に入ることができます。
一方、社会保険上の扶養は、一般的に年収が130万円未満であることが基準です。こちらは経費を差し引く前の「収入(売上)」で判断されることが多く、基準も加入している健康保険組合によって異なります。業務委託に切り替える際は、必ず配偶者の勤務先を通じて、健康保険組合に詳細な条件を確認しましょう。
6.2 育休や産休はどうなるの?
業務委託契約は雇用契約ではないため、労働基準法に基づく産前産後休業や、育児・介護休業法に基づく育児休業(育休)の制度は適用されません。それに伴い、雇用保険から支給される「出産手当金」や「育児休業給付金」も受け取ることはできません。
ただし、個人事業主として利用できる公的なサポートはあります。国民年金に加入している場合、産前産後期間の保険料が免除される制度があります。また、国民健康保険からは「出産育児一時金」が支給されます。収入が途絶える期間に備え、民間の保険に加入したり、計画的に貯蓄をしたりと、ご自身で準備しておくことが非常に重要になります。
6.3 確定申告は自分でできる?税理士に頼むべき?
確定申告はご自身で行うことも、税理士に依頼することも可能です。どちらを選ぶべきかは、あなたの売上規模や状況によって異なります。
売上がまだそれほど多くなく、経費の種類もシンプルな場合は、会計ソフト(freeeやマネーフォワード クラウドなど)を使えばご自身で十分に対応可能です。これらのソフトは簿記の知識がなくても帳簿付けができ、青色申告に必要な書類も簡単に作成できます。
一方で、年間売上が1,000万円を超えて消費税の課税事業者になったり、最大限の節税対策をしたいと考えたりする場合は、税理士に依頼するメリットが大きいでしょう。専門家に任せることで、正確な申告ができる安心感を得られるだけでなく、本業であるサロンワークに集中できる時間を確保できます。まずは一度、税理士の無料相談などを利用してみるのもおすすめです。
7. まとめ
雇用から業務委託への移行は、美容師としてのキャリアにおける大きな転換点です。収入アップや自由な働き方ができるメリットがある一方、開業届や確定申告、社会保険の手続きなど、全て自己責任で行う必要があります。特に税金や保険は複雑に感じがちですが、本記事で解説した手順に沿って準備を進めれば、決して難しいものではありません。正しい知識を身につけ、計画的に準備することが、業務委託美容師として成功するための第一歩です。この記事があなたの新しいスタートを後押しできれば幸いです。