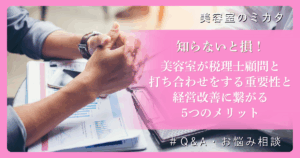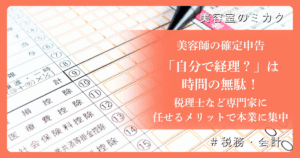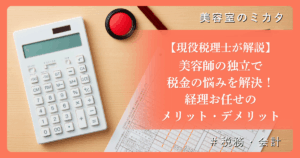【税理士監修】美容室の内装工事どうすれば経費計上できるのか考える|減価償却から仕訳まで完全ガイド

美容室の内装工事費用は、高額なだけに正しく経費計上し節税につなげたいものです。この記事を読めば、税務上の判断基準である「資本的支出」と「修繕費」の違いから、減価償却の仕組み、金額別の特例を使った有利な経費化の方法まで理解できます。工事費用は原則、資産として減価償却しますが、条件次第で一括経費にすることも可能です。税理士監修のもと、具体的な仕訳例を交えてわかりやすく解説します。
1. 美容室の内装工事費用は経費計上できるのか まずは結論から
美容室の開業やリニューアルにおいて、内装工事は大きな投資となります。「この高額な費用を経費にできれば、税金の負担を大きく減らせるのに…」とお考えのオーナー様も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、美容室の内装工事費用は経費として計上することが可能です。ただし、支払いをした年に全額を一度に経費にできるわけではなく、会計上のルールに則った適切な処理が求められます。ここでは、まずその大枠となる考え方について解説します。

1.1 原則は資産計上し減価償却で経費化する
内装工事のように、その効果が1年以上にわたって持続する支出は、原則として「資産」として会計処理します。そして、その資産の価値が時間とともに減少していくという考え方に基づき、「減価償却」という手続きを通じて、法定耐用年数に応じて数年間に分割して費用計上していくことになります。
つまり、工事費用を支払った年に一括で経費にするのではなく、工事によって得られる効果が続く期間にわたって、毎年少しずつ経費として計上していくのが基本的なルールです。これにより、期間ごとの損益をより正確に把握することができます。
1.2 条件を満たせば一括で経費計上できる特例もある
原則は減価償却による分割計上ですが、例外も存在します。中小企業者等を対象とした特例制度などを活用することで、一定の金額以下の内装工事費用であれば、その年に一括で経費として計上することが認められる場合があります。
この特例を適用できれば、その年の利益を圧縮し、納税額を抑えるといった短期的な節税効果が期待できます。どのような工事が対象になるのか、金額の基準はどうなっているのかについては、後の章で詳しく解説していきます。まずは「原則は分割、特例なら一括」という2つのパターンがあることを押さえておきましょう。
2. 経費計上の判断基準「資本的支出」と「修繕費」の違い
美容室の内装工事費用を経費として計上する際、その支出が「資本的支出」と「修繕費」のどちらに該当するのかを正しく判断することが極めて重要です。この区分によって会計処理の方法が大きく異なり、納税額にも影響を与えます。もし判断を誤ると、税務調査で指摘を受ける可能性もあるため、両者の違いを正確に理解しておきましょう。
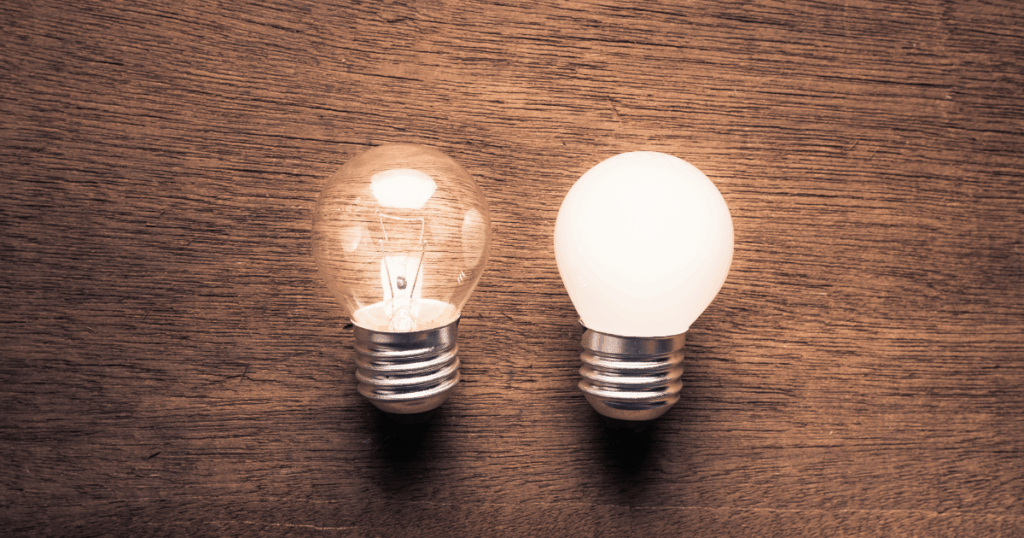
2.1 資産価値を高める工事は「資本的支出」
資本的支出とは、工事によって固定資産の価値を高めたり、使用可能な期間を延長させたりする支出を指します。つまり、単なる修理やメンテナンスの範囲を超え、資産そのものを改良し、より良くするための「投資」と見なされるものです。資本的支出に該当する場合、その費用は一括で経費にすることはできず、原則として資産に計上し、後述する「減価償却」という手続きを経て数年間にわたって費用化していきます。
美容室の内装工事における資本的支出の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 店舗の間取りを大幅に変更するリノベーション工事
- 集客力向上を目的とした、デザイン性の高い壁紙や床材への全面的な張り替え
- 新たにシャンプースペースを増設するための工事
- 性能が格段に向上する最新の空調設備や給排水設備の導入
- 防火、防水、冷暖房設備などの追加設置
これらの工事は、店舗の機能性やデザイン性を向上させ、資産価値を明らかに高めるものと判断されるため、資本的支出として処理されます。
2.2 原状回復が目的の工事は「修繕費」
一方、修繕費とは、事業用の資産を維持管理するため、あるいは元の状態に戻す(原状回復)ためにかかった費用のことです。資産の価値を高めるのではなく、あくまでも通常の機能を維持するための「メンテナンス」費用と位置づけられます。修繕費に該当する支出は、その全額を支出した事業年度の経費として一括で計上することが可能です。
美容室の内装工事における修繕費の具体例は以下の通りです。
- 汚れたり破れたりした壁紙の一部分の張り替え
- ひび割れた窓ガラスや鏡の交換
- 壊れたドアノブや照明器具の修理・交換
- 既存のシャンプー台やエアコンの故障に伴う部品交換や修理
- 床の一部分にできた傷の補修
このように、あくまでもマイナスをゼロに戻すための工事が修繕費となります。ただし、工事内容によっては資本的支出か修繕費かの判断が難しいケースも少なくありません。迷った場合は、契約書や請求書の内訳を細かく確認し、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
3. 美容室の内装工事を考える上で必須の減価償却の知識
美容室の内装工事にかかった費用は、原則としてその年に全額を経費にすることはできません。高額な内装工事は、長期間にわたってお店の収益に貢献する「資産」と見なされるためです。そこで重要になるのが「減価償却」という会計処理です。ここでは、内装工事費を経費化していくために不可欠な減価償却の基本を、わかりやすく解説します。

3.1 減価償却とは 資産の価値を年数に応じて費用化する手続き
減価償却とは、時間の経過や使用によって価値が減少していく固定資産の取得費用を、その資産が使用できる期間(法定耐用年数)にわたって分割し、毎年少しずつ経費として計上していく会計上の手続きのことです。内装や設備は、完成した瞬間から少しずつ劣化していきます。その価値の減少分を、毎年の経費として計上することで、正確な利益を計算し、税金の負担を適正化するのが減価償却の目的です。一度に大きな費用を計上するのではなく、事業の実態に合わせて費用を配分するための重要なルールと覚えておきましょう。
3.2 内装工事の勘定科目と法定耐用年数
減価償却を計算する上で最も重要なのが、工事内容をどの「勘定科目」に分類し、それぞれ何年の「法定耐用年数」で償却するかです。法定耐用年数とは、税法で定められた資産を使用できると見積もられる期間のことで、この年数に基づいて減価償却費を計算します。内装工事は、大きく「建物」と「建物附属設備」に分けられます。
3.2.1 建物
「建物」に分類されるのは、店舗の壁紙(クロス)の張り替え、床材の変更、天井の造作、間仕切り壁の設置など、建物そのものと一体化していて、構造的に分離できない内装工事が該当します。これらの内部造作の耐用年数は、建物の構造や用途によって異なりますが、美容室のような店舗の場合、一般的に10年〜15年程度で設定されるケースが多く見られます。
3.2.2 建物附属設備
「建物附属設備」とは、建物に固定されてはいるものの、建物本体とは区別される設備のことです。美容室の内装工事では、こちらに該当するものが数多くあります。工事の見積書や請求書で内訳を明確に分け、それぞれ適切な耐用年数で計上することが節税につながる重要なポイントです。
- 電気設備:照明器具、配線工事、コンセントの増設など(耐用年数15年)
- 給排水・衛生設備:シャンプー台の給排水管工事、トイレの設置など(耐用年数15年)
- ガス設備:給湯器の設置など(耐用年数15年)
- 冷暖房設備(空調設備):業務用エアコンの設置など(耐用年数13年または15年 ※出力による)
- 換気設備:換気扇やダクトの設置など(耐用年数15年)
3.3 減価償却費の計算方法 定額法と定率法
減価償却費の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」の2種類があります。どちらを選択するかで、毎年の経費計上額が変わってきます。
定額法
定額法は、毎年同じ金額を減価償却費として計上する方法です。計算式は「取得価額 × 定額法の償却率」となり、非常にシンプルです。個人事業主の場合、原則としてこの定額法で計算します。毎年の費用額が一定のため、事業計画や資金繰りの見通しが立てやすいのがメリットです。
定率法
定率法は、資産を取得した初年度の減価償却費が最も多くなり、年々その金額が減少していく方法です。計算式は「未償却残高 × 定率法の償却率」となります。法人の場合は、税務署に届出をすることで定率法を選択できます。開業初期に多くの経費を計上し、利益を圧縮したい場合に有利な方法と言えます。
4. 【金額別】美容室の内装工事をどうすれば経費計上できるのか
美容室の内装工事にかかった費用は、その金額によって経費計上の方法が大きく異なります。会計処理を誤ると、税務調査で指摘されたり、思わぬ追徴課税が発生したりする可能性もあります。ここでは、工事費用を「取得価額」として捉え、金額別にどのような経費計上ができるのか、具体的な選択肢をわかりやすく解説します。適切な会計処理は、健全な経営と効果的な節税につながる重要なポイントです。

4.1 10万円未満の場合 消耗品費として一括経費に
内装工事にかかった費用、つまり取得価額が10万円未満の場合は、「少額の減価償却資産」として、工事が完了し事業の用に供した年度に全額を経費として計上できます。例えば、部分的な壁紙の補修や、小さな造作棚の設置などがこれに該当します。この場合、資産として計上する必要はなく、「消耗品費」や「修繕費」といった勘定科目で一括して費用処理することが可能です。手続きが最もシンプルで、すぐに経費化できるため、キャッシュフローの観点からも有利な方法です。
4.2 10万円以上20万円未満の場合 一括償却資産として3年で経費に
取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、「一括償却資産」という制度を選択できます。これは、本来の法定耐用年数にかかわらず、取得価額の合計額を3年間で均等に割って経費計上する方法です。例えば、18万円のパーテーション設置工事を行った場合、毎年6万円ずつを3年間にわたって経費にできます。個別の減価償却計算が不要で、資産管理が簡便になるメリットがあります。法定耐用年数が3年より長い資産でも、短期間で費用化できるため、早期に経費を計上したい場合に有効な選択肢となります。
4.3 30万円未満の場合 少額減価償却資産の特例で一括経費に
青色申告書を提出している中小企業者等(資本金が1億円以下の法人など)であれば、「少額減価償却資産の特例」を活用できます。この特例を適用すると、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、年間合計300万円を上限として、取得した年度に全額を経費(損金)に算入することが可能です。例えば、25万円の業務用エアコンの設置工事や、28万円のシャンプー台の入れ替え工事などが対象となります。利益が多く出た年度にこの特例を活用すれば、大きな節税効果が期待できます。ただし、適用を受けるためには確定申告書に明細書を添付する必要があるなど、一定の要件を満たす必要があります。
4.4 30万円以上の場合 原則通り減価償却
取得価額が30万円以上となる内装工事は、原則的な会計ルールに従って処理します。具体的には、まず工事費用を「建物」や「建物附属設備」などの固定資産として資産計上し、その後、それぞれの法定耐用年数にわたって分割して経費化(減価償却)していきます。例えば、店舗全体のリニューアルに300万円かかった場合、その工事内容に応じて資産を分類し、定められた耐用年数(例:10年、15年など)で毎年減価償却費を計算し、経費として計上します。一度に大きな費用を計上することはできませんが、長期にわたって安定的に経費を計上していくことになります。
5. 具体例でわかる 美容室の内装工事の仕訳方法
ここでは、美容室の内装工事に関する会計処理を、具体的な金額と勘定科目を使った仕訳例で解説します。理論だけでなく実際の処理方法を見ることで、経費計上への理解を深めましょう。

5.1 内装工事費150万円を支払った場合の仕訳
30万円以上の内装工事は、原則として固定資産として計上し、減価償却によって数年にわたり経費化します。ここでは、店舗の内部造作工事に150万円を普通預金から支払ったケースを想定します。
工事が完了し、引き渡しを受けた日付で資産として計上します。
【工事完了・支払時の仕訳】
(借方)建物附属設備 1,500,000円 / (貸方)普通預金 1,500,000円
この仕訳により、150万円が会社の資産(建物附属設備)として計上されたことになります。この時点ではまだ経費にはなっていません。この後、決算時に減価償却を行うことで、費用として計上していきます。
5.2 決算時に減価償却費を計上する際の仕訳
次に、上記で資産計上した150万円の内装工事について、決算時に減価償却を行う際の仕訳です。ここでは、法定耐用年数15年、償却方法は定額法(毎年同じ金額を償却する方法)で計算します。
【減価償却費の計算】
1,500,000円 ÷ 15年 = 100,000円
【決算時の仕訳】
(借方)減価償却費 100,000円 / (貸方)建物附属設備 100,000円 (※直接法)
または
(借方)減価償却費 100,000円 / (貸方)減価償却累計額 100,000円 (※間接法)
この仕訳によって、資産価値の減少分である10万円が、その年度の経費(減価償却費)として計上されます。一般的には、資産の取得価額を分かりやすく管理できる間接法が多くの企業で採用されています。
5.3 25万円の空調設備工事に特例を適用した場合の仕訳
青色申告をしている中小企業者等であれば、「少額減価償却資産の特例」を利用できます。これは、取得価額が30万円未満の資産について、全額をその事業年度の経費として一括で計上できる制度です。
ここでは、25万円の業務用エアコン設置工事を行い、普通預金から支払ったケースを考えます。
【工事完了・支払時の仕訳】
(借方)消耗品費 250,000円 / (貸方)普通預金 250,000円
この特例を適用することで、本来は資産計上と減価償却が必要な25万円の支出を、支払ったその年に全額経費として処理できます。これにより、その年の利益を圧縮し、節税効果を早く得ることが可能になります。なお、この特例を適用した資産については、固定資産台帳に登録し、摘要欄に「少額減価償却資産」と記載して管理することが重要です。
6. 美容室の内装工事の経費計上で注意すべきポイント
美容室の内装工事費用を経費として計上する際には、いくつかの重要な注意点があります。会計処理の判断を誤ると、税務調査で指摘を受け、追徴課税の対象となる可能性も否定できません。ここでは、特に注意すべき3つのポイントを具体的に解説します。

6.1 居抜き物件の内装工事はどう考えるか
開業費用を抑えるために居抜き物件を活用するケースは多いですが、会計処理は新規(スケルトン)物件よりも複雑になる傾向があります。居抜き物件の場合、前のテナントが残した内装や設備(造作)を買い取ることが一般的です。この造作の取得費用は、新たに行った内装工事費用とは区別し、資産として計上する必要があります。
その上で、自身が追加で行った工事の内容によって経費計上の方法が変わります。例えば、既存の壁紙や床材を新しいものに張り替えるといった原状回復や維持管理が目的の工事は「修繕費」として一括で経費にできる可能性があります。しかし、間取りを大きく変更したり、新たな機能を付け加えたりする工事は、資産価値を高める「資本的支出」と判断され、減価償却の対象となります。居抜き物件の工事では、どの部分が資産の取得で、どの部分が修繕費・資本的支出にあたるのかを契約書や請求書の内訳で明確に区分しておくことが極めて重要です。
6.2 個人事業主と法人での取り扱いの違い
内装工事費用を経費計上する際の基本的な考え方、つまり「資本的支出」と「修繕費」の判断基準や減価償却の仕組みは、個人事業主と法人で違いはありません。しかし、利用できる税制上の特例に違いが生じる場合があります。
代表的な例が「少額減価償却資産の特例」です。これは取得価額30万円未満の資産を一括で経費にできる制度ですが、適用できるのは青色申告を行う中小企業者等に限られます。美容室の規模であれば、青色申告をしている個人事業主も法人の多くもこの対象となりますが、白色申告の個人事業主は適用できません。また、赤字が発生した場合の繰越控除の期間(個人事業主は3年、法人は原則10年)など、長期的な視点での違いも存在します。ご自身の事業形態でどの制度が利用できるのかを正確に把握しておくことが大切です。
6.3 税務調査に備えて契約書や請求書は必ず保管する
美容室の内装工事は高額な支出となるため、税務調査の際には重点的にチェックされる項目の一つです。経費計上の正当性を客観的に証明するため、工事に関する証拠書類は絶対に保管しなければなりません。保管すべき書類には、工事請負契約書、見積書、請求書、領収書などが含まれます。
特に重要なのが、工事内容の詳細がわかる請求書の内訳です。請求書の記載が「内装工事一式」となっていると、どの工事が修繕費でどれが資本的支出なのかを税務署に説明できません。最悪の場合、全額が資産計上すべきと判断されるリスクもあります。工事を依頼する段階で、業者に「壁紙張替え」「空調設備設置」「配管工事」といったように、具体的な項目ごとに金額を記載した詳細な請求書の発行を依頼しましょう。これらの書類は、法人の場合は原則7年間、個人事業主の場合は青色申告なら7年間、白色申告なら5年間の保管義務があります。
7. まとめ
美容室の内装工事費は、原則として資産計上し、法定耐用年数に応じた減価償却によって経費化します。しかし、工事の目的が原状回復であれば「修繕費」として、また取得価額が30万円未満であれば青色申告を条件に「少額減価償却資産の特例」を適用することで、一括で経費計上することも可能です。適切な会計処理は健全な経営と節税に繋がります。判断に迷う場合は税理士に相談し、税務調査に備えて契約書や請求書は必ず保管しましょう。