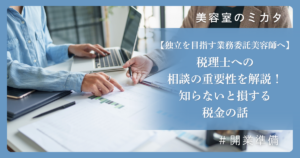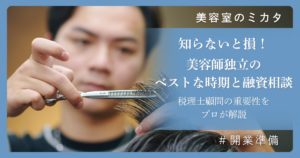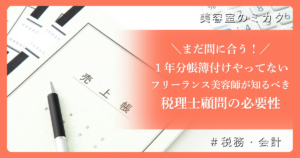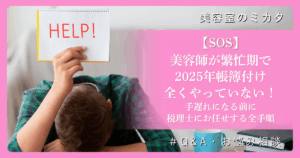美容室開業でスタッフを雇うなら必須!労働保険の加入手続きのすべて
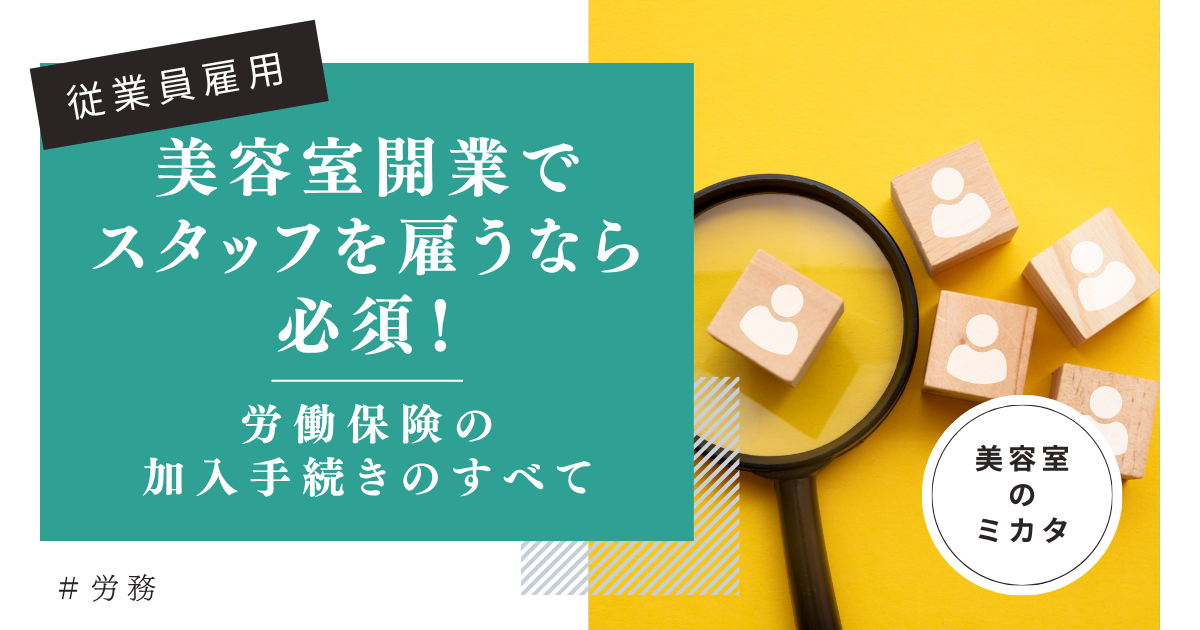
美容室を開業しスタッフを1人でも雇う場合、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入は法律で定められた義務です。この記事を読めば、加入対象となるスタッフの条件から、労働基準監督署やハローワークで行う具体的な手続きの流れ、必要書類、保険料の計算方法まで、開業時に必要な知識がすべてわかります。罰則のリスクを避け、大切なスタッフとお店を守るために、正しい手順を理解しましょう。
1. 美容室開業で労働保険の加入は義務?対象となるスタッフの条件
美容室の開業準備を進める中で、「労働保険って必ず入らないといけないの?」「どんなスタッフを雇ったら手続きが必要になるの?」といった疑問をお持ちのオーナー様も多いのではないでしょうか。ここでは、労働保険の加入義務と、対象となるスタッフの具体的な条件について分かりやすく解説します。

1.1 結論:スタッフを1人でも雇うなら労働保険の加入は法律上の義務
まず結論からお伝えすると、美容室を開業し、スタッフを一人でも雇用する場合、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入は法律で定められた事業主の義務です。これは、法人の美容室はもちろん、個人事業主として開業する場合も同様で、事業の規模や業種に関わらず適用されます。「知らなかった」では済まされない、オーナーとして必ず押さえておくべき重要なルールです。
1.2 パート・アルバイトも対象!労働保険の加入が必要なスタッフの条件
「労働保険」と一括りにされますが、これは「労災保険」と「雇用保険」という2つの制度の総称です。重要なのは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトであっても、条件を満たせば加入義務の対象となる点です。そして、この2つの保険では対象となるスタッフの範囲が少し異なります。
1.2.1 全ての労働者が対象となる「労災保険」
労災保険は、業務中や通勤中のケガ、病気などから労働者を保護するための保険です。そのため、雇用形態(正社員、パート、アルバイト、日雇いなど)や労働時間、国籍に関わらず、賃金を受け取る全ての労働者が対象となります。たとえ1日だけの短期アルバイトのアシスタントを雇った場合でも、労災保険の適用対象となることを覚えておきましょう。
1.2.2 一定の条件を満たす労働者が対象となる「雇用保険」
雇用保険は、労働者が失業した際の生活の安定などを目的とした保険です。労災保険とは異なり、加入には以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
例えば、「週3日、1日7時間勤務のパートスタイリスト」であれば、週の労働時間は21時間となり、長期雇用が見込まれるため、雇用保険の加入対象となります。この2つの条件を両方満たすスタッフは、雇用保険の被保険者として手続きが必要です。
1.3 オーナー自身や同居の親族は原則として対象外
事業主であるオーナー自身や、オーナーと生計を同一にする同居の親族(配偶者、子、父母など)は、原則として「労働者」とはみなされないため、労働保険の対象外です。ただし、業務の実態によっては労働者と判断されるケースもあります。また、これらの立場の方でも、万が一の業務災害に備えたい場合には、任意で労災保険に加入できる「特別加入制度」も用意されています。
2. 労働保険とは?労災保険と雇用保険の2つの制度を解説
美容室を開業し、スタッフを雇用する際に必ず理解しておかなければならないのが「労働保険」です。労働保険とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の2つを総称した言葉であり、政府が管掌する強制保険制度です。スタッフを一人でも雇用する事業主は、業種や規模を問わず、原則として加入が義務付けられています。
この制度は、働くスタッフの生活を守るための重要なセーフティーネットです。美容室オーナーとして、スタッフが安心して働ける環境を提供するためにも、それぞれの保険の役割を正しく理解しておきましょう。

2.1 業務中や通勤中のケガに備える労災保険
労災保険は、スタッフが業務中や通勤中にケガ、病気、障害、あるいは不幸にも死亡した場合に、必要な保険給付を行う制度です。美容室の現場では、シャンプーによる手荒れ、カラー剤によるアレルギー、カット中のハサミによるケガ、あるいは通勤途中の交通事故など、様々なリスクが潜んでいます。
労災保険に加入していれば、このような業務上または通勤上の災害に遭ったスタッフに対して、治療費や休業中の生活を支えるための給付金が支給されます。この保険の大きな特徴は、パートやアルバイトといった雇用形態に関わらず、すべての労働者が対象となる点です。また、保険料は全額事業主が負担します。
2.2 スタッフの失業に備える雇用保険
雇用保険は、スタッフが失業して収入がなくなった場合に、再就職までの生活を支え、安定した求職活動を支援するための制度です。一般的に「失業手当」と呼ばれる基本手当の給付がよく知られています。
美容室を退職したスタッフが、次の職場を見つけるまでの間の経済的な不安を和らげる役割を果たします。また、育児や介護で休業する際の給付金なども雇用保険から支給されます。労災保険とは異なり、雇用保険には加入要件があり、「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」スタッフが対象となります。保険料は、事業主とスタッフの双方が負担する仕組みです。
3. 美容室開業における労働保険の加入手続き 完全ガイド
スタッフを雇用して美容室を開業する場合、労働保険の加入手続きは避けて通れません。手続きには順番があり、提出先や期限もそれぞれ異なります。ここでは、オーナーが迷わず手続きを進められるよう、具体的な流れを4つのステップに分けて詳しく解説します。

3.1 STEP1 労働保険関係成立届の提出
労働保険の手続きで、最初に行うべきことが「労働保険関係成立届」の提出です。これは、美容室という事業所が労働保険(労災保険)の適用事業所になったことを届け出るための重要な手続きです。スタッフを一人でも雇用した時点で、この手続きの義務が発生します。
3.1.1 提出先は労働基準監督署
「労働保険関係成立届」の提出先は、開業する美容室の所在地を管轄する労働基準監督署です。ハローワークではないので注意しましょう。管轄の労働基準監督署がどこか不明な場合は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
3.1.2 提出期限と必要書類
提出期限は非常に短く設定されています。手続きをスムーズに進めるためにも、事前に必要書類を準備しておきましょう。
【提出期限】
保険関係が成立した日(最初のスタッフを雇用した日)の翌日から10日以内
【主な必要書類】
- 労働保険関係成立届
- 【法人の場合】登記事項証明書(履歴事項全部証明書など)のコピー
- 【個人事業主の場合】事業主世帯全員の住民票、事業所の賃貸借契約書のコピーなど事業の実態がわかる書類
3.2 STEP2 労働保険概算保険料申告書の提出と納付
STEP1の「労働保険関係成立届」と同時に、「労働保険概算保険料申告書」を提出し、保険料を納付する必要があります。これは、その年度末までにスタッフへ支払う賃金総額の見込み額から概算の労働保険料を算出し、前払いする形で申告・納付する手続きです。
3.2.1 保険料の計算方法と申告書の書き方
概算保険料は「賃金総額の見込み額 × 労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)」で計算します。美容業の労働保険料率は年度によって改定される可能性があるため、必ず最新の料率を確認してください。申告書は労働基準監督署で受け取るか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。記入方法がわからない場合は、窓口で相談しながら作成すると安心です。
【提出・納付期限】
保険関係が成立した日の翌日から50日以内
申告書を労働基準監督署または都道府県労働局、日本銀行に提出し、発行される納付書を使って金融機関や郵便局の窓口で保険料を納付します。
3.3 STEP3 雇用保険適用事業所設置届の提出
労災保険の手続きが完了したら、次は雇用保険の手続きに移ります。まずは、美容室が雇用保険の適用事業所であることを届け出る「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。この手続きは、雇用保険の加入対象となるスタッフを初めて雇用した場合に必要となります。
3.3.1 提出先はハローワーク
ここからの手続きの窓口は、労働基準監督署ではなくハローワーク(公共職業安定所)に変わります。提出先は、美容室の所在地を管轄するハローワークです。
3.3.2 提出期限と必要書類
こちらも期限が短いため、迅速な対応が求められます。STEP1、2で提出した書類の控えが必要になるので、大切に保管しておきましょう。
【提出期限】
事業所を設置した日(初めて雇用保険の被保険者を雇用した日)の翌日から10日以内
【主な必要書類】
- 雇用保険適用事業所設置届
- 労働保険関係成立届の事業主控
- 登記事項証明書(法人の場合)や事業所の賃貸借契約書(個人事業主の場合)など
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)など
3.4 STEP4 雇用保険被保険者資格取得届の提出
最後の手続きは、雇用するスタッフ一人ひとりを雇用保険に加入させるための「雇用保険被保険者資格取得届」の提出です。通常、STEP3の「適用事業所設置届」と同時に行います。
3.4.1 スタッフごとに行う手続き
この届出は、雇用保険の加入条件を満たすスタッフ全員分を作成し、提出する必要があります。加入条件は原則として「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」ことです。パートやアルバイトのスタッフでも、この条件を満たせば加入義務があります。
【提出期限】
資格取得の事実があった日(雇用した日)の属する月の翌月10日まで
【手続き後の流れ】
手続きが完了すると、ハローワークから「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。このうち「雇用保険資格取得等確認通知書」は、速やかにスタッフ本人へ渡してください。
4. オーナーや家族従業員は加入できる?労働保険の特別加入制度
労働保険は、原則として「労働者」を保護するための制度です。そのため、事業主であるオーナーや、オーナーと生計を同一にする家族従業員は労働者に該当せず、加入義務の対象外となります。しかし、スタッフと同じように現場で働くオーナーや家族にも、業務中のケガのリスクは当然あります。そこで、任意で労災保険に加入できる「特別加入制度」が用意されています。
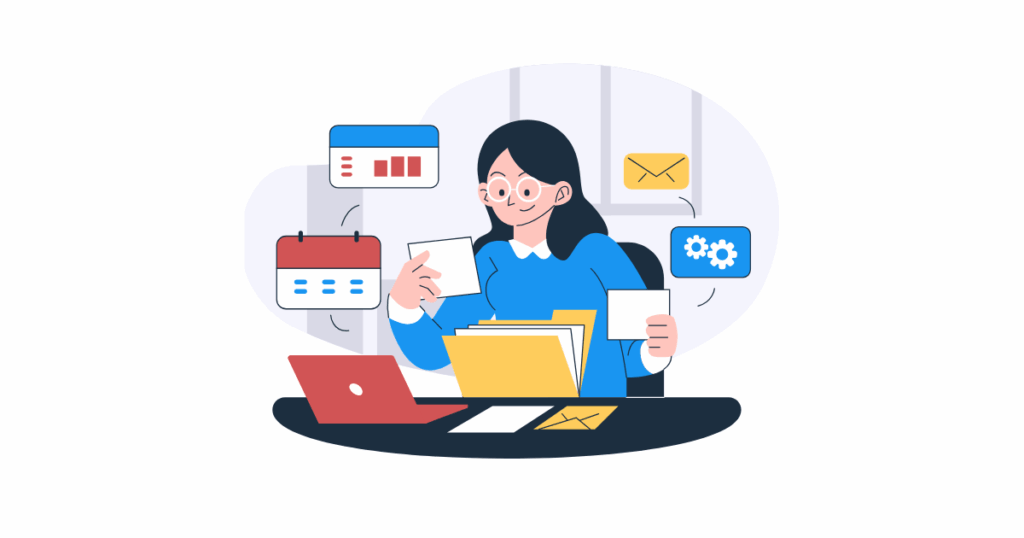
4.1 労災保険の「特別加入制度」とは
特別加入制度とは、労働者ではないものの、業務の実態などから労働者に準じて保護することがふさわしいと認められる人が、特別に労災保険に任意で加入できる制度です。美容室のオーナーや家族従業員も、一定の要件を満たせばこの制度を利用できます。
この制度に加入することで、万が一業務中や通勤中にケガをしたり、病気になったりした場合に、労働者と同様の保険給付を受けることができ、安心して事業に専念できます。
4.1.1 特別加入できる人の条件
美容室の開業において、労災保険の特別加入制度の対象となるのは、主に以下のような方々です。
- 中小事業主
常時使用する労働者が100人以下の美容室の個人事業主や法人の代表者が該当します。ただし、労働者を一人も雇用していない一人親方の場合は加入できません。 - 事業主の家族従事者
中小事業主と生計を同一にし、事業に従事している家族(配偶者、子、父母など)も対象です。 - 法人の役員
中小事業主である法人の代表者以外の役員も、業務の実態に応じて加入できます。
4.1.2 特別加入の手続き方法
特別加入の手続きは、通常の手続きとは異なり、「労働保険事務組合」に事務処理を委託して行うのが一般的です。労働保険事務組合とは、事業主に代わって労働保険に関する事務手続きを代行する、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
まずは地域の商工会議所や業界団体などが運営する労働保険事務組合を探し、加入を申し込みます。その後、組合を通じて「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署に提出し、承認されれば加入手続きは完了です。
保険料は、加入者が自身の所得水準などを考慮して選択する「給付基礎日額」に基づいて決定されます。
4.2 雇用保険は原則として加入できない
労災保険には特別加入制度がありますが、雇用保険については、事業主や法人の役員、事業主と生計を同一にする家族従業員は原則として加入できません。雇用保険は、あくまで労働者が失業した場合の生活保障を目的とした制度であるためです。
そのため、オーナー自身や家族従業員が店を辞めたとしても、失業手当(基本手当)を受け取ることはできない点を理解しておく必要があります。
5. 労働保険の加入手続きを怠った場合のリスクと罰則
「忙しくて後回しに…」「一人だけだから大丈夫だろう…」そんな軽い気持ちで労働保険の加入手続きを怠ると、事業の存続を揺るがしかねない重大なリスクを負うことになります。ここでは、手続きを怠った場合に科される具体的な罰則と経営上のデメリットを解説します。

5.1 遡っての保険料徴収と重い追徴金
労働保険の加入義務があるにもかかわらず手続きを怠っていた場合、行政機関の指導によって最大2年間に遡って保険料を徴収されます。さらに、本来納めるべきだった保険料に加えて、ペナルティとして「追徴金」が課せられます。納付が遅れれば「延滞金」も発生し、金銭的な負担は雪だるま式に膨れ上がってしまいます。
5.2 労災事故発生時の莫大な費用負担
最も恐ろしいリスクが、未加入期間中にスタッフが業務中や通勤中にケガをしてしまったケースです。本来であれば労災保険から治療費や休業補償などが給付されますが、未加入の場合はそうはいきません。事業主は、労災保険から給付された金額の全額または一部を費用として徴収されることになります。事故の規模によっては、この費用が数百万円、数千万円にのぼることもあり、美容室の経営に壊滅的なダメージを与える可能性があります。
5.3 ハローワークからの指導と刑事罰の可能性
労働保険の未加入が発覚した場合、まずは労働基準監督署やハローワークから加入を促す指導が入ります。この指導に正当な理由なく従わないなど、悪質なケースと判断された場合は、法律に基づく罰則が適用されることもあります。例えば、雇用保険法では「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性が定められています。
5.4 スタッフの信頼を失い採用活動にも悪影響
法律上の罰則だけでなく、経営上のリスクも見過ごせません。労働保険に加入していないという事実は、スタッフに「自分たちの安全や生活を守ってくれない会社だ」という不信感を抱かせます。結果として、離職率の悪化やモチベーションの低下につながるでしょう。また、SNSや口コミサイトで「ブラック企業」という評判が広まれば、新しい人材の採用も極めて困難になります。優秀なスタイリストを確保し、お店を成長させていく上で、労働保険への加入は最低限の責務と言えます。
6. 手続きは専門家に任せるべき?社会保険労務士に依頼するメリット
労働保険の加入手続きは、書類の準備や行政機関への提出など、煩雑で時間がかかる作業です。特に、オープン準備で忙しい美容室のオーナー様にとっては、大きな負担となり得ます。そこで選択肢となるのが、労働・社会保険の専門家である「社会保険労務士(社労士)」への依頼です。
費用はかかりますが、それを上回るメリットも多く存在します。ここでは、社労士に手続きを依頼するメリットと、自分で手続きする場合との違いについて解説します。

6.1 社会保険労務士(社労士)とは?
社会保険労務士(社労士)とは、労働関連の法律や社会保険制度に関する国家資格を持つ専門家です。企業経営における「人」に関するエキスパートであり、労働保険・社会保険の手続き代行、就業規則の作成、給与計算、労務相談、助成金の申請代行など、幅広い業務を行います。
6.2 社労士に依頼する3つの大きなメリット
労働保険の加入手続きを社労士に依頼することで、主に3つの大きなメリットが得られます。
6.2.1 1. 煩雑な手続きから解放され、本業に集中できる
最大のメリットは、時間と手間を大幅に削減できることです。労働保険の手続きには、労働基準監督署やハローワークなど、複数の窓口へ出向く必要があります。また、専門用語が多く、慣れない書類作成に戸惑うことも少なくありません。
社労士に依頼すれば、これらの手続きをすべて代行してもらえます。オーナー様は、サロンワーク、スタッフ教育、集客といった美容室の売上に直結する本来の業務に集中することができます。
6.2.2 2. 正確・迅速な手続きで安心感を得られる
労働保険の手続きには、法律で定められた期限があります。万が一、書類に不備があったり、提出が遅れたりすると、追徴金などのペナルティが課されるリスクがあります。また、法改正も頻繁に行われるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。
専門家である社労士に任せれば、法改正にも適切に対応し、正確かつ迅速に手続きを完了してくれます。法令遵守(コンプライアンス)の観点からも、安心して事業をスタートできるでしょう。
6.2.3 3. 開業後の労務管理まで見据えたサポートが受けられる
社労士の役割は、単なる手続き代行だけではありません。スタッフを雇用すれば、給与計算や勤怠管理、万が一の労務トラブルへの対応など、様々な課題が発生します。
顧問契約を結ぶことで、日々の労務に関する相談役として、事業運営を継続的にサポートしてもらえます。就業規則の作成や、活用できる助成金の提案など、美容室の健全な発展に繋がるアドバイスを受けることも可能です。
6.3 依頼費用の目安と注意点
社労士への依頼費用は、契約形態によって異なります。手続きを一度だけ依頼する「スポット契約」と、継続的な相談や手続きを依頼する「顧問契約」が一般的です。
スポット契約の場合、労働保険の新規適用手続き(関係成立届や適用事業所設置届など)で数万円程度が相場です。顧問契約は、従業員数に応じて月額数万円からとなります。
社労士を選ぶ際は、費用だけでなく、美容業界の実情に詳しいか、コミュニケーションが取りやすいかといった点も重要なポイントです。複数の事務所から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
7. まとめ
美容室を開業し、スタッフを1人でも雇用する場合、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入は法律で定められた事業主の義務です。手続きは労働基準監督署やハローワークへの届出など複数のステップがあり、期限も定められています。加入を怠ると罰則が科されるだけでなく、スタッフが安心して働ける環境を損なうことにも繋がります。手続きに不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効です。スタッフを守り、健全なサロン経営の第一歩として、計画的に手続きを進めましょう。