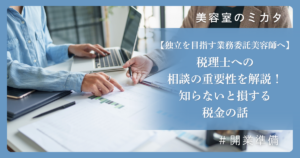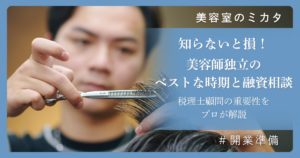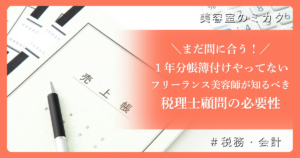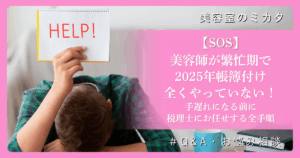美容室ではじめて従業員を雇用する時の給与の注意点【完全ガイド】失敗しないためのチェックリスト付
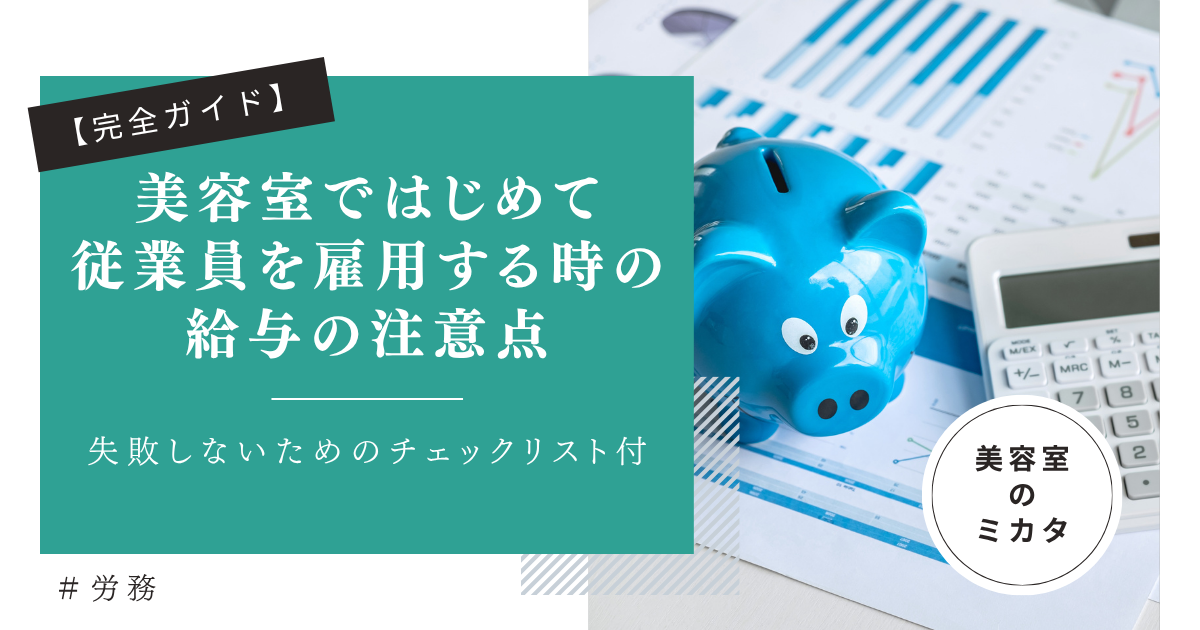
はじめて従業員を雇う美容室オーナー様へ。給与設定は法律や社会保険が絡み、トラブルが不安ですよね。この記事を読めば、美容師の給与相場から固定給・歩合給の決め方、雇用契約書の作り方まで、失敗しないための知識が全てわかります。結論、法律を守りつつ従業員が納得する明確なルール作りが、人材定着とサロン成長の鍵です。付属のチェックリストを活用し、安心して最初の一歩を踏み出しましょう。
1. 美容室で従業員を雇用する前に知るべき給与の基礎知識
はじめて従業員を雇用するオーナー様にとって、給与設定は最も頭を悩ませる問題の一つです。適正な給与を支払うことは、優秀な人材の確保や定着、スタッフのモチベーション維持に直結します。まずは、給与を決める上で土台となる基本的な知識をしっかりと押さえておきましょう。

1.1 美容師の給与相場はいくら?スタイリストとアシスタントの違い
給与額を設定する最初のステップは、業界の給与相場を把握することです。美容師の給与は、役職や経験、地域によって大きく異なります。特に、お客様を担当できる「スタイリスト」と、その補助業務を行う「アシスタント」では、給与水準に明確な差があります。
一般的に、アシスタントの月給は都市部で約18万円〜22万円、地方で約16万円〜20万円が相場です。一方、スタイリストになると個人の売上も反映されるため幅が広がり、月給約25万円〜40万円以上が目安となります。もちろん、これはあくまで平均的な数値です。自店のエリアの競合店の求人情報をリサーチし、地域相場を把握した上で、お店のコンセプトやターゲット層に合わせた給与水準を検討することが重要です。
1.2 給与体系の種類と特徴を解説(固定給・歩合給・ミックス型)
美容室の給与体系は、主に「固定給制」「歩合給制」「ミックス型(固定給+歩合給)」の3種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、お店の方針や従業員のキャリアプランに合った制度を選びましょう。
1.2.1 固定給制
毎月決まった額の給与が支払われる制度です。売上に関わらず収入が安定するため、特にアシスタントや入社間もないスタイリストにとっては安心して働けるというメリットがあります。オーナー側も給与計算がしやすいですが、個人の頑張りが給与に直接反映されにくいため、モチベーションを維持するための評価制度などが別途必要になる場合があります。
1.2.2 歩合給制(フルコミッション)
売上の一定割合がそのまま給与となる制度です。成果がダイレクトに収入に繋がるため、トップスタイリストのモチベーションを最大限に引き出せる可能性があります。しかし、収入が不安定になりやすく、雇用契約の場合は労働時間に対して最低賃金を下回ることが許されないため、労働基準法との兼ね合いで導入には細心の注意が必要です。一般的には業務委託契約で採用されることが多い形態です。
1.2.3 ミックス型(固定給+歩合給)
多くの美容室で採用されているのがこのミックス型です。保証された固定給に加えて、個人の売上や指名数、店販売上などに応じた歩合給(インセンティブ)が上乗せされます。従業員の生活の安定と、仕事へのモチベーションを両立できるバランスの取れた制度と言えるでしょう。歩合の計算方法をどう設計するかが、制度をうまく機能させる鍵となります。
1.3 これだけは守るべき給与に関する法律(最低賃金・労働基準法)
従業員を雇用する以上、オーナーは法律で定められたルールを守る義務があります。知らなかったでは済まされない重要な法律が「最低賃金制度」と「労働基準法」です。トラブルを未然に防ぐため、必ず確認してください。
1.3.1 最低賃金制度
最低賃金とは、国が定める賃金の最低額のことです。都道府県ごとに金額が定められており、毎年改定される可能性があります。時給換算した際に、この最低賃金額を下回る給与設定は法律違反となり、罰則の対象となります。これは、固定給制はもちろん、歩合給制であっても同様です。必ず自店の所在地の最新の最低賃金を確認しましょう。
1.3.2 労働基準法(賃金支払いの5原則)
労働基準法では、給与の支払い方について以下の5つの原則を定めています。
- 通貨払いの原則:給与は現金(通貨)で支払う必要があります。(例外:本人の同意を得た上での口座振込)
- 直接払いの原則:給与は代理人ではなく、従業員本人に直接支払わなければなりません。
- 全額払いの原則:所得税や社会保険料など法律で定められたもの以外は、給与から天引きしてはいけません。(例外:労使協定がある場合)
- 毎月1回以上払いの原則:給与は毎月1回以上、定期的に支払う必要があります。
- 一定期日払いの原則:「毎月25日」のように、支払日を具体的に定めて支払わなければなりません。
これらの原則は、従業員の安定した生活を守るための基本的なルールです。給与の支払い日を毎月変更したり、備品代などを一方的に給与から天引きしたりすることは認められません。
2. 【ステップ別】はじめて従業員を雇用する際の給与の決め方
従業員の給与を決定するプロセスは、サロン経営の根幹をなす重要な作業です。ここでは、はじめて従業員を雇用するオーナー様が、体系的かつ公正な給与制度を構築できるよう、4つの具体的なステップに分けて解説します。従業員のモチベーションを高め、長く活躍してもらうための土台を一緒に作りましょう。

2.1 ステップ1 基本給と各種手当を設定する
給与の核となるのが「基本給」です。これは、役職や個人の成績に関わらず、労働の対価として毎月固定で支払われる賃金を指します。基本給は、都道府県ごとに定められた最低賃金を必ず上回る金額に設定しなければなりません。地域の美容師の給与相場や、採用したい人材の経験・スキルを考慮して、適切な金額を決定しましょう。そして、基本給に加えて、従業員の努力や役割を評価するために各種手当を設定します。
2.1.1 技術手当や店販手当など美容室ならではの手当
美容室の給与制度では、技術力や売上への貢献度を評価する独自の手当が重要です。これにより、従業員のスキルアップや販売意欲を促進できます。
- 技術手当:スタイリストのランク(ジュニアスタイリスト、トップスタイリストなど)や、ヘアセット・着付けといった特定のスキルに応じて支給します。技術を磨くことへのインセンティブになります。
- 店販手当:シャンプーやトリートメントなどの店販品の売上に対し、一定の割合を還元する手当です。サロンの物販売上向上に直結します。
- 指名手当(指名料):お客様からの個人指名に対して支払われる手当です。スタイリストの人気や顧客満足度を直接給与に反映できます。
2.1.2 役職手当や通勤手当の考え方
サロンの組織運営や従業員の生活を支えるための基本的な手当も整備しましょう。
- 役職手当:店長やマネージャーなど、責任のある役職に就く従業員に対して支給します。役職の重責に見合った金額を設定することが、組織の秩序を保つ上で大切です。
- 通勤手当:従業員の通勤にかかる交通費を補助する手当です。「月額2万円まで」のように上限を設けて実費を支給するのが一般的です。公共交通機関のほか、マイカー通勤を認める場合はガソリン代の支給ルールも明確にしておきましょう。
- その他:必要に応じて、住宅手当や家族手当などを設けることも、福利厚生を充実させ、人材の定着につなげる有効な手段です。
2.2 ステップ2 歩合給(インセンティブ)のルールを設計する
歩合給は、個人の売上実績に応じて給与が変動する仕組みで、従業員のモチベーションを大きく左右します。歩合給を導入する際は、誰が見ても公平で分かりやすいルールを設計することが不可欠です。
主な歩合給には、個人の技術売上や店販売上に対して一定の料率を乗じて支給する「売上歩合」があります。料率の設定は非常に重要で、サロンの利益を確保しつつ、従業員が「頑張れば報われる」と感じられる絶妙なバランスを見つける必要があります。例えば、「指名売上の10%」「フリー売上の5%」といった形で、売上の種類によって料率を変える方法も効果的です。
歩合の計算対象となる売上を「税抜価格」にするのか「税込価格」にするのか、クーポン利用による割引分をどう扱うのかなど、細かなルールを事前に明確にし、雇用契約書に記載しておくことで、後のトラブルを未然に防げます。
2.3 ステップ3 残業代の計算方法と固定残業代制度の注意点
労働基準法では、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて労働させた場合、割増賃金(残業代)を支払う義務があります。練習会やミーティングなども、強制参加であれば労働時間とみなされるため注意が必要です。
残業代は「1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間」で計算します。時間外労働の割増率は25%以上、深夜労働(22時~翌5時)はさらに25%以上が加算されます。
美容室でよく採用されるのが「固定残業代(みなし残業代)制度」です。これは、毎月一定時間分(例:20時間分)の残業を想定し、その分の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う制度です。しかし、固定残業代制度を導入する場合、設定した時間を超えて残業が発生した際には、その超過分の残業代を別途支払わなければなりません。また、雇用契約書や給与明細に「基本給◯円、固定残業代(◯時間分)◯円」のように、基本給と固定残業代部分を明確に分けて記載することが法律で義務付けられています。この記載がないと、制度自体が無効と判断されるリスクがあります。
2.4 ステップ4 社会保険・労働保険料の計算と給与からの天引き
従業員を一人でも雇用した場合、事業主は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)に加入する義務があります。これらの保険料は、事業主と従業員がそれぞれ決められた割合で負担します。
従業員の給与からは、社会保険料や労働保険料の従業員負担分を天引き(控除)します。これに加えて、所得税と住民税も源泉徴収して国や自治体に納付する必要があります。給与から天引きする主な項目は以下の通りです。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 所得税
- 住民税
これらの保険料率や税金の計算は専門的な知識を要し、法改正によって変更されることも頻繁にあります。計算ミスは従業員との信頼関係を損なう原因となるため、給与計算ソフトを導入したり、社会保険労務士(社労士)や税理士といった専門家に手続きを依頼したりすることを強くおすすめします。
3. 給与支払いでトラブルを回避するための重要書類
美容室経営において、給与に関するトラブルは従業員のモチベーション低下や離職に直結する深刻な問題です。口約束だけで雇用を進めてしまうと、後々「言った・言わない」の水掛け論に発展しかねません。オーナーと従業員の双方が安心して働くためには、給与条件を明確に記した書面を取り交わすことが不可欠です。ここでは、トラブルを未然に防ぐために絶対に作成すべき「雇用契約書」と「給与明細」について、その重要性と記載すべき項目を具体的に解説します。

3.1 雇用契約書に必ず明記すべき給与関連の項目
雇用契約書(または労働条件通知書)は、労働条件についてオーナーと従業員が合意したことを証明する重要な書類です。特に金銭が絡む給与関連の項目は、誰が見ても誤解が生じないよう、具体的かつ詳細に記載する必要があります。
労働基準法では、以下の給与に関する項目を必ず書面で明示することが義務付けられています。
- 賃金の決定、計算および支払いの方法
- 賃金の締切りおよび支払の時期
- 昇給に関する事項
これらの法定義務に加え、美容室ならではのトラブルを防ぐためには、以下の点を網羅的に記載することが推奨されます。
- 基本給:月給、日給、時給の別と具体的な金額を明記します。
- 各種手当:技術手当、店販手当、役職手当、皆勤手当、通勤手当など、支給するすべての手当について、その名称、計算方法、支給条件を具体的に定めます。
- 歩合給(インセンティブ):歩合給を導入する場合、売上の何パーセントを支給するのか、指名売上とフリー売上で料率が違うのかなど、計算ルールを詳細に記載します。対象となる売上の定義(税抜/税込、店販商品を含むかなど)も明確にしておきましょう。
- 時間外労働手当(残業代):法定の割増率(1.25倍以上)に基づく計算方法を明記します。固定残業代(みなし残業代)制度を導入する場合は、その金額と、その金額に含まれる残業時間数(例:月20時間分を固定残業代として支給)、そしてそれを超えた場合は別途残業代を支払う旨を必ず記載してください。
- 賃金からの控除:社会保険料や税金など、法律で定められたもの以外(例:積立金や親睦会費など)を給与から天引きする場合は、労使協定の締結と、その旨の記載が必要です。
これらの項目を曖昧にせず、一つひとつ丁寧に書面に落とし込むことが、将来の紛争を避けるための第一歩となります。
3.2 給与明細の正しい作り方と法律で定められた記載事項
従業員へ給与を支払う際には、給与明細を交付することが所得税法で義務付けられています。給与明細は、単なる支払額の通知書ではありません。従業員が自身の給与がどのように計算されたのかを正確に把握し、会社との信頼関係を築くための重要なコミュニケーションツールです。
給与明細には、主に「支給」「控除」「勤怠」の3つの情報を記載する必要があります。
- 支給項目:基本給、歩合給、残業手当、通勤手当など、支給されるすべての金額の内訳を記載します。合計額である「総支給額」も明記します。
- 控除項目:健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料といった社会保険料、そして源泉所得税、住民税など、給与から天引きする項目の内訳を記載します。合計額である「控除額合計」も必要です。
- 勤怠項目:給与計算の基礎となる情報です。出勤日数、総労働時間、時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間、有給休暇の取得日数と残日数などを記載します。
そして最後に、総支給額から控除額合計を差し引いた「差引支給額(手取り額)」を明記します。これらの項目が正確に記載された給与明細を毎月きちんと交付することで、給与計算の透明性を確保し、従業員の納得感と安心感を高めることができます。
4. 従業員の給与に関するよくある質問 Q&A
はじめて従業員を雇用する美容室オーナーが抱えがちな、給与に関する疑問についてQ&A形式でわかりやすく解説します。トラブルを未然に防ぐためにも、基本的なルールをしっかり押さえておきましょう。

4.1 試用期間中の給与は本採用時より低くても問題ない?
はい、試用期間中の給与を本採用時よりも低く設定すること自体は法的に問題ありません。ただし、そのためにはいくつかの重要な条件を満たす必要があります。
まず、雇用契約書や労働条件通知書に「試用期間中は月給〇〇円(本採用時の〇〇%)」といった形で、給与額が異なることを明確に記載し、従業員の合意を得ておく必要があります。口頭での説明だけでなく、必ず書面で残すことがトラブル防止の鍵です。
最も注意すべき点は、試用期間中であっても給与が都道府県ごとに定められた最低賃金を下回ることは絶対に許されないという点です。最低賃金は必ず確認し、それを遵守した上で給与額を設定してください。
4.2 賞与(ボーナス)や退職金を支払う義務はある?
いいえ、法律上、会社に賞与(ボーナス)や退職金を支払う義務はありません。これらはあくまで会社の任意で設ける制度です。
ただし、就業規則や雇用契約書に「年2回賞与を支給する」「勤続3年以上の従業員には退職金を支払う」などの規定を設けた場合は、その記載内容に基づいた支払義務が発生します。もし賞与を支給する場合は、「会社の業績に応じて支給する」といったように、支給条件を明確に定めておくと良いでしょう。
従業員のモチベーション維持や長期的な人材定着のために導入を検討する価値はありますが、一度制度として定めると一方的に廃止することは難しいため、導入は慎重に判断する必要があります。
4.3 従業員が遅刻・欠勤した場合の給与計算はどうする?
従業員が遅刻や欠勤をした場合、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、働かなかった時間分の給与を差し引く(控除する)ことができます。
月給制の場合の具体的な計算方法は、就業規則などで定めておく必要があります。一般的には、「月給額 ÷ その月の所定労働時間 × 遅刻・欠勤の時間数」という計算式で控除額を算出します。
注意点として、遅刻や欠勤に対するペナルティとして「罰金」を科す場合は、労働基準法で定められた「減給の制裁」にあたります。この場合、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また減給総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならないという上限が定められています。単なる不就労時間の控除と、制裁としての減給は明確に区別して対応しましょう。
5. 【保存版】美容室の従業員給与で失敗しないためのチェックリスト
これまでの内容を踏まえ、美容室で初めて従業員を雇用する際に、給与関連で失敗しないための最終チェックリストを作成しました。各項目を一つずつ確認し、安心してスタッフを迎え入れられる準備を整えましょう。

5.1 雇用前に確認する項目リスト
求人募集を開始する前に、オーナーとして必ず確認・決定しておくべき foundational な項目です。特に法律に関わる部分は、後々のトラブルを避けるための最重要ポイントです。
□ 管轄の労働局が発表している最新の「地域別最低賃金」を確認しましたか?
□ 労働基準法で定められた法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)と休憩、休日のルールを理解していますか?
□ スタイリスト、アシスタントなど、募集する役職の給与相場をリサーチしましたか?
□ 社会保険(健康保険・厚生年金)と労働保険(雇用保険・労災保険)の加入義務があるか確認しましたか?
□ 自店の経営状況や事業計画に基づいた、無理のない人件費の予算を立てていますか?
5.2 給与体系を決定する際の項目リスト
スタッフのモチベーションに直結する給与体系を具体的に設計するためのチェックリストです。明確で公平なルール作りが、従業員の定着率を高める鍵となります。
□ 給与体系は「固定給」「歩合給」「ミックス型」のどれを採用するか決定しましたか?
□ 基本給の金額は、最低賃金や相場を考慮して設定しましたか?
□ 歩合給を導入する場合、その計算方法(例:指名売上の〇%、フリー売上の〇%)と料率を明確に定めましたか?
□ 技術手当、店販手当、役職手当など、美容室ならではの手当の支給基準と金額は決まっていますか?
□ 通勤手当は実費支給か、上限を設けるかなどルールを決めましたか?
□ 固定残業代(みなし残業代)を導入する場合、その金額に含まれる残業時間数を明記する準備はできていますか?
□ 昇給の条件やタイミング、評価基準について定めていますか?
□ 賞与(ボーナス)を支給する場合、その算定基準や支給時期を決めていますか?
5.3 契約・手続きで確認する項目リスト
採用が決定してから、実際に給与を支払うまでの事務手続きに関するチェックリストです。書類の不備は信頼関係を損なう原因になるため、正確に進めましょう。
□ 雇用契約書(または労働条件通知書)に、給与の決定、計算・支払方法、締切・支払日を正確に記載しましたか?
□ 給与明細に記載が義務付けられている項目(基本給、各種手当、控除額など)をすべて網羅していますか?
□ 社会保険・労働保険の加入手続きに必要な書類は準備できていますか?
□ 源泉徴収する所得税や住民税の計算方法を理解していますか?
□ 試用期間を設ける場合、その期間と期間中の給与について本人に説明し、契約書に明記しましたか?
□ 給与計算を自力で行うか、給与計算ソフトを利用するか、専門家(税理士や社労士)に依頼するかを決めましたか?
6. 給与計算や手続きに不安なら専門家(社労士)への相談も有効
ここまで給与に関する様々なルールを解説してきましたが、「正直、複雑で自信がない」「本業のサロンワークが忙しくて手が回らない」と感じるオーナー様も少なくないでしょう。給与計算や社会保険の手続きは、少しの間違いが従業員との信頼関係を損ねたり、法的なトラブルに発展したりする可能性のある非常に重要な業務です。そんな時は、人事・労務管理の専門家である社会保険労務士(社労士)に相談・依頼することも有効な選択肢です。

6.1 社労士とは?美容室オーナーの労務をサポートする専門家
社会保険労務士(社労士)とは、労働関連の法律や社会保険に関する専門知識を持つ国家資格者です。従業員の採用から退職までに発生する様々な手続きや、健全な職場環境を作るための就業規則の作成、労務トラブルの予防・解決などをサポートしてくれます。はじめて従業員を雇用する美容室オーナーにとって、頼れるパートナーとなってくれる存在です。
6.2 社労士に依頼できる主な業務内容
社労士には、美容室の給与・労務に関する幅広い業務を依頼できます。具体的には以下のような業務が挙げられます。
- 給与計算の代行:毎月の煩雑な給与計算を、法律に則って正確に代行してもらえます。残業代や保険料の計算ミスを防ぎます。
- 社会保険・労働保険の手続き:従業員の入社・退社時に必要な健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの複雑な手続きをすべて任せられます。
- 就業規則・雇用契約書の作成や見直し:サロンの実態に合った、法的に有効な就業規則や雇用契約書を作成し、労務リスクを低減します。
- 助成金の申請サポート:美容室が活用できる可能性のある雇用関連の助成金について、情報提供から申請手続きまでサポートを受けられます。
- 労務トラブルに関する相談:従業員との間で万が一トラブルが発生した際に、専門的な視点からアドバイスをもらい、円満な解決を目指せます。
6.3 社労士に依頼する3つの大きなメリット
専門家に業務を委託(アウトソーシング)することには、コストがかかる一方で、それを上回るメリットがあります。
6.3.1 メリット1:オーナーが本業のサロンワークに集中できる
最も大きなメリットは、時間と手間のかかる事務作業から解放されることです。慣れない給与計算や役所への手続きに費やしていた時間を、技術の向上やお客様へのサービス、売上アップのための施策など、サロンの成長に直結するコア業務に集中して使えるようになります。
6.3.2 メリット2:法改正への対応と労務リスクの回避
労働関連の法律は頻繁に改正されます。知らず知らずのうちに法律違反をしていた、という事態は避けなければなりません。社労士に依頼すれば、常に最新の法改正に対応した適切な労務管理が実現でき、労働基準監督署の調査などにも安心して備えられます。
6.3.3 メリット3:助成金を活用できる可能性がある
国や自治体は、雇用の安定や職場環境の改善に取り組む事業主に対して様々な助成金を用意しています。しかし、その種類は多く、申請手続きも複雑です。専門家である社労士のサポートを受けることで、自店で活用できる助成金を見つけ、受給できる可能性が高まります。
6.4 社労士への依頼形態と費用の考え方
社労士への依頼には、主に2つの形態があります。
- 顧問契約:月額費用を支払い、給与計算や各種手続き、日常的な労務相談など、継続的にサポートを受ける契約形態です。
- スポット契約:就業規則の作成や助成金の申請など、特定の業務を単発で依頼する契約形態です。
費用は、従業員数や依頼する業務範囲によって大きく異なります。まずは複数の社労士事務所に見積もりを依頼し、サービス内容と費用を比較検討することをおすすめします。初回相談は無料で行っている事務所も多いため、一度話を聞いてみるだけでも、自店の課題を整理する良い機会になるでしょう。
7. まとめ
美容室で初めて従業員を雇用する際の給与設定は、採用の成功と従業員の定着、ひいてはサロン経営の安定に直結する最重要事項です。本記事で解説した給与相場や労働基準法などの法律遵守はもちろん、サロンの方針に合った給与体系を慎重に設計することが不可欠です。明確なルールと適切な手続きは、従業員との信頼関係を築き、無用なトラブルを未然に防ぎます。付属のチェックリストを活用し、不安な点は社会保険労務士などの専門家にも相談しながら、健全なサロン経営を目指しましょう。